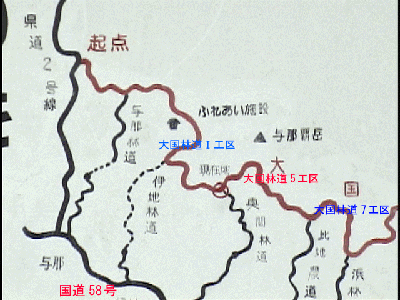
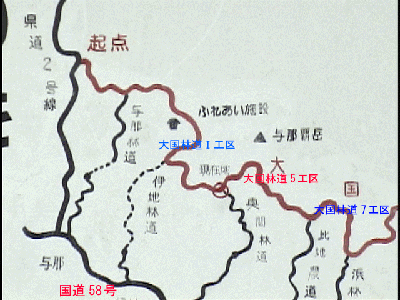
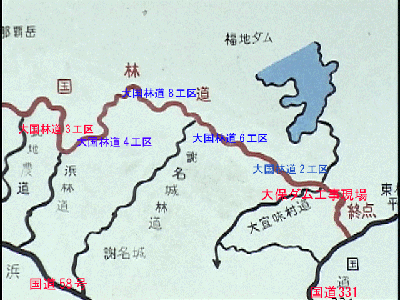
11-4 広域基幹林道大国線の概要 広域基幹林道大国線は、国頭村字与那の県道2号線を起点として、大宜味村字大保の国道331号 線に至る全体延長35.5km、総事業費45億9千6百万円、利用区域面積3,648haの林道である。 この林道は、昭和52年度に国頭村字与那地内において156mの開設事業を手始めに、昭和55年度 には林道終点側の大宜味村字大保地内から第2工区の開設を、さらに、昭和59年度に第3工区、昭 和62年度に第4及び第5工区、昭和63年度に第6工区、平成元年度に第7、8工区と開設工区を増 やし大国全線の早期開通をめざした。 また、平成2年度に第3工区の比地川支流において大国橋(橋長69m)の架橋を実施するととも に、平成3年度に第7工区の比地川本流において、大国林道の最終開設区間に長尾橋(横長133m) を架設することにより、昭和52年度に開設事業着工以来17年の年月を要した本林道の開設事業も平 成5年度に全線開通の運びとなった。 当該林道は国頭地域県道2号線以南の骨格的な路線となることから開設工事施工中から小動物の 生態に配慮してきているところであるが、今後とも小動物への配慮を強化していく計画である。1999年9月19日の沖縄タイムスより
11.林 道 11-1 林道事業の概要 林道は、林業の合理的な経営及び森林の集約的な管理のための基幹的施設であるばかりでなく山 村地域の生活道として、また森林レクリエーション施設にも利用され、いわゆる多面的な機能を有 している。 特に本県の林道は、木材の搬出施設としての役割のみならず、造林事業、森林管理あるいは、集 落間の連絡道路として農山村地域の振興に果たす役割は大きいも、のがある。 北部地域の林道網の整備状況は、近年逐次整備されてきたが、平成8年度末現在での林道密度は 2.6m/haにすぎない。 なお、林道事業には、公益的機能の高度発揮や林業経営の基盤の整備を推進する森林保全整備事 業、保険・文化・教育的な利用の推進、都市や農山村の良好な生活環境の保全・創出のための森林 整備等を実施する森林環境整備事業、林業用機械が消費する揮発油の税に相当する財源をもって実 施する農林漁業用揮発油税財源身替林道整備事業がある。 目的別に林道の新設・改築を目的とする林道開設事業、既設林道の局部的構造の質的向上・自然 環境の保全を目的とする林道改良事業、既設林道の機能向上を図るための林道舗装事業があり、そ れぞれ国庫補助を受けて県及び市町村が施工主体となって事業を実施している。また市町村等への 助成策については、林道開設事業が9/10(国8/10、県1/10)、林道改良事業が7/10(国5/10、県2/10・ 国3/10、県4/10)、林道舗装事業が7/10(国5/10、県2/10・国10/30、県11/30)の補助率で助成して いる。
11-5 広域基幹林道奥与郡線の概要10 広域基幹林道奥与那線は、国頭村宇佐手の県道2号線を起点として照首山林道、我地佐手林道(一 部)、楚洲林道(一部)、造林作業道、伊江林道(一部)、奥1号林道を編入して、奥の集落南側に至 る総延長14.6Kmの全幅5.Omの林道である。 この林道は、平成5年度から照首山林道と奥1号林道の一部から工事着手し、平成8年度末までに 12,565mを整備されており、平成9年度には完了の計画である。
10.治 山 10-1治山事業の概要 治山事業は森林の維持、造成を通じて山地に起因する災害から県民の生命・財産を保全し、水源のかん養、 生活環境の保全・形成等を図る重要な県土保全政策の一つである。 事業実施にあたっては、山地に起因する災害のおそれがある森林地域を保安林に指定し事業を実施してい る。 事業実施にあたっては、第9次治山事業7箇年計画(平成9年~平成15年度)に則して執行している。
9.保 安 林 9-1保安林の概要 保安林面積は森林面積の11.1% に当る4,945haである。そのうち水源かん養保安林が72%を占め ており、潮害防備保安林8%、干害防備保安林7%、土砂流出防備保安林6.6%、その他となって いる。 近年森林の有する公益的機能を期待する社会的要請に応えるため、保健保安林479haか指定され ており、県民の憩いの場として、生活環境保全林整備事業が実施され、今帰仁村の乙羽岳、伊江 村字東江前、名護市の多野岳、恩納村の県民の森が整備されている。
4.林地開発許可制度 4-1本制度の趣旨 森林は、災害の防止、水害の防止、水源のかん養、環境の保全といった公益的機能を有してい る。特に近年の社会経済情勢の変化に伴い、森林の有する自然環境の保全及び形成等公益的機能の 発揮に対する要請が一段と高まっている。 また、森林は公益的機能と合わせて木材生産等の経済的機能を有しており、この両機能の総合的 かつ、高度な発輝を確保することは、国民生活の安定と地域社会の健全な発展にとって従来にも増 して重要となっている。 これらの要請とあいまって、社会情勢の変化は国土の開発を招き、その進展は都市近郊から農山 村へと広範囲に及んでおり、その結果、各地域において災害のおそれや環境の破壊等の観点から問 題視されるものがでてきた。 森林法においては、従来から特に公益的機能の要請の強い森林については保安林制度により、そ の保全及び形成に努めてきたところであるが、それ以外の森林においては自由に開発行為を行いう るという問題があった。 このようなことに対処するため、昭和49年に森林法が改正され「民有林における開発行為の許可 制」が導入され、国民の要請に応えることになった。 4-2 本地域の現状と課題 本地域の民有林面積は全県の60%を占め、本県林業の中心的役割を果たしている一方、重要な水 資源地域であり、更に貴重な動・植物の生息地であるなど機能の高い森林が多いことから、指導の 徹底を図り、開発行為の審査等にあたっては特に慎重を期す必要がある。 なお、開発行為の処理状況は昭和63年度の22件、223haをピークに減少傾向を示し、特徴として 農用地の造成(43.1%)とゴルフ場の設置(32.9%)が全面積の76%を占めている。
1.北部地域の概要 1-1北部地域の概要 北部地域は、沖縄本島の北部に位置し、3離島を含む1市2町9村からなり、地域面枕は82,307ha、県土 面積の36.3%を占め、古来より「山原」と呼称されている地域である。 地勢は、沖縄本島では比較的山岳が発達し与那覇岳(503m)をはじめ西銘岳、伊湯岳、名護岳等300m~40 0m級の山々が北東から南西に縦走しており、内陸部は丘陵台地を形成し海岸まで迫っている。離島の伊平屋 島には200m級の山岳があるがその他の島は平坦台地である。 水系としては福地川(19.1km)、安波川(11.1km)、普久川(8.8km)、新川川(8.11m)が太平洋に注い でおり、又東支那海に注いでいる河川は大保川(11.6km)、源河川(10.6km)、羽地大川(9.6km)等が主 な河川である。 地質は大部分が古生層の粘坂岩、砂岩からなっている。土壌は国頭マージで被われ、強酸牲で有機質に乏 しく生産性が低いうえ、土壌養分の流出が激しい。 気温は年平均22℃、冬期平均気温は15℃で、月別の最高最低の気温差は少ない。又月平均温度も高い。降 水量は年間を通じて多く2,000mmを超えるが年毎の差が大きい。